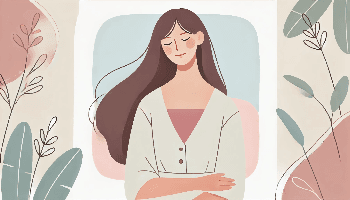人間関係の中で「この人ならこうしてくれるはず!」と期待していたのに、まったく応えてもらえなかったとき、ガッカリするだけでなく、イライラしてしまうこともある。
1. なぜ期待しすぎるのか?
人は「こうあるべき」「これくらいやってくれるだろう」と、自分の価値観を基準に期待してしまう。でも、相手にも相手の事情や価値観があるため、自分の期待通りに動いてくれるとは限らない。
よくあるケース
- 友達が「助けてくれる」と思っていたのに、冷たくされた。
- 上司が「ちゃんと評価してくれる」と思っていたのに、スルーされた。
- パートナーが「これくらい察してくれるはず」と思ったのに、気づいてくれなかった。
2. 期待しすぎることで生まれるストレス
期待したことが実現しないと、「なんで?」「どうして分かってくれないの?」と不満がたまり、人間関係がぎくしゃくする。特に、自分が相手に対して好意的であればあるほど、裏切られたような気持ちになる。
対処法
- 期待する前に「相手は本当にそれをしてくれる人なのか?」を考える。
- 「これをしてくれたら嬉しい」と事前に伝えておく。
- 期待を「やってくれたらラッキー」くらいに考えるクセをつける。
期待されるとプレッシャーでうまくできない不安
逆に、自分が誰かに期待されることでプレッシャーを感じ、思うように行動できなくなることもある。
1. 期待されることで生まれる不安
「期待される」というのは本来うれしいことのはず。でも、その期待に応えなければならないと感じると、失敗への恐怖が強くなり、余計にうまくできなくなる。
よくあるケース
- 「君ならできるよ!」と言われた途端、ミスが怖くなる。
- 「頼んでよかった!」と言われると、次もうまくやらないとと思ってしまう。
- 「あなたに期待してる」と言われると、完璧じゃないとダメな気がする。
2. プレッシャーを減らす考え方
期待に応えようとする気持ちは大事だけど、それがストレスになりすぎると逆効果。うまくプレッシャーをコントロールすることが必要。
対処法
- 「期待される=100%完璧にしなきゃ」ではなく、70%くらいの出来でもOKと考える。
- 「失望されるかも」ではなく、「自分ができる範囲でベストを尽くそう」と思う。
- 期待に応えられなくても「これが今の自分の限界だった」と受け止める。
期待と現実のバランスを取るには?
結局、人間関係の中で「期待する・される」のバランスが大事。期待しすぎるとストレスになるし、期待を完全にゼロにすることも難しい。
✔ 相手に求めすぎず、してもらえたら感謝する
✔ 期待されることを「信頼の証」と捉えつつ、完璧を求めすぎない
✔ 他人の期待より、自分のペースを大事にする
期待と現実のギャップをうまく乗り越えることで、人間関係のストレスを減らし、もっと楽に生きられるかもしれない。