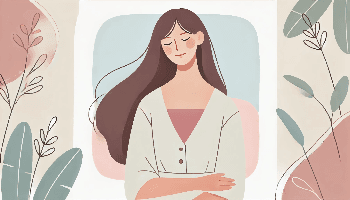はじめに
ストレスがたまると眠れない。眠れないと、さらにストレスがたまる。この悪循環に悩まされている人は少なくありません。この記事では、ストレスと睡眠の関係をわかりやすく解説し、質のいい眠りを手に入れるための具体的な方法を紹介します。
1. ストレスが睡眠に与える影響
■ 神経が興奮して寝つきが悪くなる
ストレスによって交感神経が優位になると、リラックスできず入眠までに時間がかかるようになります。
■ 睡眠の質が低下する
夜中に目が覚めたり、眠りが浅くなったりする原因にも。これが続くと心身ともに疲れが取れません。
■ 体内時計が乱れる
ストレスによる生活リズムの乱れが、メラトニンの分泌低下や眠気のタイミングのズレを引き起こします。
2. 睡眠不足がストレスを悪化させる理由
■ 感情のコントロールが難しくなる
睡眠が足りないと脳の働きが鈍り、怒りや不安に過敏になります。
■ ストレスホルモンが増加する
慢性的な睡眠不足は、コルチゾールなどのストレスホルモンを増やし、心身に悪影響を与えます。
■ 自律神経が乱れる
交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、リラックスしにくくなります。
3. 睡眠の質が下がる原因と対策
■ 夜中にトイレで目が覚める場合
夜中にトイレに行きたくなって、ふと目が覚めてしまうことはありませんか?
そんな状況が続くと、深い睡眠が妨げられ、翌日の疲れやストレスの回復が不十分になる原因になります。
特に、寝る直前まで水分を多く摂っている場合、夜間の排尿回数が増える傾向があります。
睡眠の質を保つためには、就寝の1〜2時間前までに水分補給を済ませておくのが理想的です。
どうしてものどが渇くときは、ひと口程度にとどめると、トイレで目覚めにくくなります。
また、夕食での塩分の摂りすぎや、夜のカフェイン・アルコールも影響するため、全体的な生活習慣を見直すことも効果的です。
■ 就寝前のルーティンを決める
スマホを見ない、ぬるめの入浴、軽いストレッチなど、寝る前にリラックスできる行動を習慣にしましょう。
たとえば「寝る前はスマホを置いて、お茶を飲みながらストレッチする」といったシンプルな習慣でも十分です。
■ 寝室環境を整える
照明を暗めにする、温度・湿度を適切に保つ、静かな環境をつくることで眠りやすくなります。
■ カフェインやアルコールを控える
特に夕方以降はカフェインやアルコールを避けることで、深い眠りを妨げにくくなります。
4. 睡眠の質を高めるサポートアイテム
■ サプリメントの活用
■ 音・香り・光を活かす
- 癒し系BGM、アロマ(ラベンダーなど)、間接照明などが効果的
■ スマートフォンの使用制限
- ブルーライトを避ける・夜は通知を切るなど、脳を刺激しない工夫を
まとめ
睡眠とストレスは密接に関係しており、どちらかが乱れるともう一方にも悪影響を与えます。だからこそ、ストレス対策として「眠りの質を整える」ことは非常に重要です。
まずは簡単にできる習慣から取り入れて、少しずつ睡眠の質を高めていきましょう。